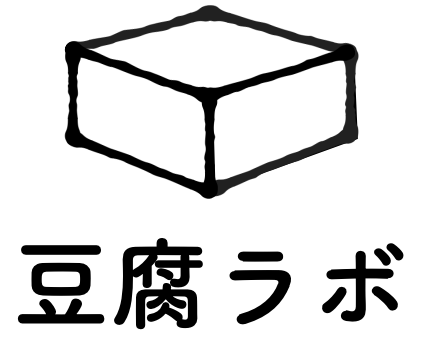にがりについてまとめた記事です。
【わかること】
- にがりとは
- にがりの作り方
- にがりの使い方
- にがりの種類
- にがりの飲み方
にがりとは

にがりとは、豆腐を製造するときに使われる原材料です。具体的には、「塩化マグネシウム」や「硫酸カルシウム」を主原料にする液体、粉のことを指します。
にがりは、「とうふ用凝固剤」とも呼ばれ、漢字で「苦汁」と書かれることもあります。
にがり|作り方

にがりの作り方は、次の2種類あります。
- 海水を濃縮する製法
- 人工的に合成する製法
海水を濃縮する製法
海水を蒸発させ、濃縮して作る製法は、にがりの伝統的な製造方法です。海水を煮詰めてできた、ミネラル分を多く含む液体。複雑な成分比で各種ミネラルを含んでいます。
人工的に合成する製法
塩化マグネシウムや硫酸カルシウムを化学的に合成して作られるにがりです。「塩化マグネシウム」や「硫酸カルシウム」の純度が高いのが特徴です
にがり|使い方

にがりの使い方は、次の通りです。
- 豆乳と混ぜて豆腐を作る
- 料理や飲料に混ぜてミネラル補給をする
豆乳と混ぜて豆腐を作る
にがりは、豆乳と混ぜて豆腐を作るのに使われる原材料です。
にがりに含まれている「塩化マグネシウム」「硫酸カルシウム」は、豆乳の「タンパク質(大豆タンパク質)」と出会うと、タンパク質の形を変える役割をします。
料理や飲料に混ぜてミネラル補給をする
にがりには「マグネシウム」「カリウム」などの成分が含まれており、料理や飲料に混ぜてミネラル補給をするという使い方もあります。
にがりの濃度やにがりに含まれる塩分は、にがりによって違うため、商品に書かれている適量を守ってお召し上がりください。
にがり|種類

にがりの種類によって、味・形状・できる豆腐の質感が変わってきます。
にがりには、次のような種類があります。
- 塩化マグネシウムのにがり
- 硫酸カルシウムのにがり
塩化マグネシウムのにがり

塩化マグネシウムが主成分のにがりは「伝統的な製法」で海水から作られたものが多いです。舐めてみると苦いのが特徴。
苦味の原因は「Mg 2+(マグネシウムイオン)」です。舐めると「とてつもない苦味」を感じるので、直接飲むのは避けましょう。
できる豆腐の質感・味
塩化マグネシウムが主成分のにがりを使って作った豆腐は、「甘みのある柔らかい豆腐」ができやすいです。
もちろん、温度・打ち方(にがりの混ぜ方)・熟成時間・にがりの量などの条件によって、できる豆腐は変わってきますが、大豆の「甘み」を感じて「柔らかくクリーミー」な質感・味のものができる特徴があります。
硫酸カルシウムのにがり
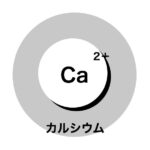
硫酸カルシウムが主成分のにがりは粉状だったり、フレーク状になっていることが多いです。使うときは、水に溶かして使います。
水に溶かした硫酸カルシウム系のにがりは舐めても「苦くない」のが特徴。粉っぽい味がしますが、全然、苦味を感じません。
できる豆腐の質感・味
硫酸カルシウムが主成分のにがりを使って作った豆腐は、「さっぱりとした味の固い質感の豆腐」ができやすいです。
食感は固めですが少し水っぽく、繊細で傷つきやすく、角が欠けやすい質感をしている豆腐ができます。
味わいは淡白な感じの味で、旨味が少なく感じることが多いです。醤油やポン酢、生姜や鰹節などで味を加えるとより美味しく食べることができます。
にがり|飲み方

にがりにはミネラル分が含まれており、体内のミネラルバランスを整えて、ダイエットのサポートとなると言われています。
にがりは「成分」「濃度」「塩分」などが、商品によって違うので、商品に記載されている飲み方・摂取量を厳守してください。
にがりの過剰摂取に注意
ですが、ここで、注意してもらいたいのが「にがりの取り過ぎ」です。塩化マグネシウムが主成分のにがりは、海水を濃縮して作られたものが多いです。
つまり、濃い海水をご飯にかけて食べているようなもの。海水を飲むと喉が乾くのと一緒で、かけ過ぎは塩分の過剰摂取にもつながり身体に悪い影響を与えます。
また、体内のマグネシウムが多くなると、下痢になる場合があるので、注意してください。また、腎臓の機能が低下している人が取ると、高マグネシウム血症が生じやすくなり、血圧低下、吐き気、心電図異常などの症状が現れることもあるので、注意しましょう。
にがり|関連記事